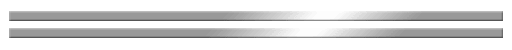
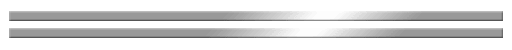
|
始めに |
|
|---|---|
| 当社は、東京都下の多摩市で創業しましたが、業務拡大に伴い、平成13年8月に東京都中央区東日本橋2丁目に東京事業所を開設いたしました。この場所を選んだ理由はいろいろあるのですが、結果的には大変よい選択だったと思います。(秋葉原も隣駅です。)とは言え、開設から半年が過ぎたものの、慌しく時が過ぎ、すぐ近くの事もまだ十分に知りません。 そこで、みなさんとこの地域のあれこれを探訪してみたいと思います。よろしければ仕事の合間にでもお付き合い下さい。いろいろ下調べをして書いていますが、そこはまだ新参もの。専門家でもありませんし間違いや勘違いもあると思います。「これはこうだ」というご指摘や「こんな所もあるぞ」という情報提供をどしどしお願いいたします。 この情報発信が、少しでも地域発展につながれば幸いです。 |
|
|
「第1回 東日本橋と両国」 平成14年4月5日 |
|
| 第1回として、事務所周辺の地名について書いてみます。 事務所の住所=東日本橋という地名は、昭和46年に日本橋両国、日本橋橘町などのいくつかの地名を合併して命名されたそうです。 ここは両国橋の中央区側になります。今でこそ「両国」といえば墨田区側を指しますが江戸時代まで遡れば橋の両側一帯を指し、中央区側が「両国広小路」、墨田区側が「向両国」と呼ばれていました。そして、「両国広小路」は江戸中で最も栄えた繁華街だったのです。 JR両国駅のすぐ、「江戸東京博物館」に、当時の両国広小路界隈のミニチュアが展示されています。それを見ると、見世物小屋が並んだ繁栄ぶりがよくわかります。 |
 中央区側「両国」についての 石碑(靖国通り沿い) |
| 中央区側の「両国」は、明治になってからも単に「両国」でしたが、昭和22年から「日本橋両国」となり、先に記した合弁により東日本橋になりました。墨田区側との混乱を避ける目的があったのかもしれませんが、由緒ある名前が消えてしまったのは残念なことです。写真の石碑は、ここも両国と呼ばれていたことを歴史に残そうと建てられたものです。 さて、そもそも両国という地名は、両国橋に由来します。墨田川に渡るこの橋は、武蔵国(江戸側)と下総国の”両国”を結ぶ橋として架けられました。竣工当時は、「大橋」と命名されていましたが下流の「新大橋」が出来た後、俗称であった「両国橋」が正式名称となりました。 この橋が架けられるきっかけは、有名な明暦の大火(1657年)です。幕府の政策により隅田川には橋がなかったため、大勢の人が火に追われても対岸に逃げることができませんでした。大火の後、政策転換により橋が架けられると共に、延焼を防ぐ広場として「広小路」が設けられました。そして「本所」や「深川」などの地域も江戸市中に組み入れられ、やがて武蔵国と下総国の境は江戸川となります。そういう新興地域と旧市街の人々が行き来する場所として、「両国広小路」は江戸一番の繁華街に成長したわけです。 思えば、我々の業界でも橋(=ブリッジ)という用語を良く使います。PCI−VMEブリッジ等は、新技術と従来技術を橋渡ししている好例です。しかし一方で、まだ十分な橋の無い川もあります。それだけでなく、逆により深い川(=デジタル・デバイド)作ってしまっている側面はないでしょうか? 当社は、及ばずながらこれらの川に「橋=ブリッジ」を架ける役目を果し、「両国共に」繁栄させる礎になれればと考えています。 |
|
![]()